「テストの点数よりも大事なものがある」と僕は直感していたのだ。
受験戦争を勝ち抜き、東京の大学に進学した僕は、映画製作に出会い、衝撃を受けた。
映画監督になるため、夜間の映像専門学校を卒業した僕は・・・
ドラマ助監督として冒険の世界へ
映像専門学校を卒業した僕は、フリーランスの助監督として、テレビドラマの現場で働き始めた。
そこで待ち受けていたのは、僕が子供のころから待ち望んでいた「冒険の世界」だった。
毎朝5時半に新宿スバルビル前に集合し、ロケバスに乗り込んで冒険の旅へと出発した。
ロケバス内で、テレビ業界では有名な「ポパイ」という業者が作る朝食弁当を急いで食べると、ロケ地に到着する。
ロケ地には、テレビで見たことのある芸能人たちが、次から次へとやってきた。
そして、芸能人と一緒に、都内のロケ場所を移動しながら、毎日終電近くまで撮影するのだ。
目の前で、キムタクや安達祐実や竹中直人らが演技する日々。
単調で退屈な学校生活とは違い、1日として同じ日はなかった。
毎日が刺激と興奮の連続だった。
だが、楽しいことばかりだったわけではない。
僕が入ったテレビの世界は、学歴の関係ない、実力主義の厳しい世界だ。
中卒や高卒の先輩もたくさんいた。
そういう人たちの中で、僕の「早稲田卒」という学歴は、かなり悪目立ちした。
僕はもともと運動神経が悪く、不器用で要領も悪い。
だから、瞬発力や頭の回転の速さが問われる現場系の仕事は苦手だった。
僕はよくロケ現場でミスをして、先輩たちから馬鹿にされた。
「早稲田のくせに」と言って、露骨に攻撃してくる人もいた。
そういう心無い先輩に負けないために、僕は必死で頑張った。
僕は、自分に何か才能があるとしたら、それは「人よりも努力できる能力」だと思う。
一刻も早くテレビの世界で認めてもらうために、僕は睡眠時間を削って誰よりもたくさん働いた。

恩師との出会い
僕が助監督になって3年くらいたったころ、僕のことを評価してくれる人物が現れた。
Tさんというテレビドラマ監督だ。
Tさんは、僕の父親くらいの年齢で、白髪にクリッとした目が特徴の快活なおじさんだ。
日本人なら誰もが知っている連続ドラマをいくつも監督し、赤坂で小さなドラマ制作会社を経営していた。
普段は優しいが、怒るとヤクザのように怖い。
Tさんの監督するドラマで僕が助監督をしたことがきっかけで、僕はTさんの会社で見習いとして雇われることになった。
月給は15万円だった。
Tさんは、毎晩のように、僕を飲みに連れて行ってくれた。
Tさんは30歳近く年上なのに、僕と友達のように接してくれた。
赤坂の居酒屋や中野のキャバクラで、僕とTさんはいつも明け方まで飲んだくれた。
そんなTさんには、2つの口癖があった。
ひとつ目は、「企画書を書け」。
Tさんが過去30年間のテレビ業界でのし上がって来れたのは、寝る間を惜しんで企画書を書き、知り合いのプロデューサーに提出しまくったおかげらしい。
100本中1本でも当たればめっけもん、というのがTさんの考え方だった。
Tさんに影響されて、半人前の助監督だった僕も、いつか監督デビューするために自分の企画を温めるようになった。
ふたつ目は、「一番になれ」。
Tさんは酔っぱらうと、いつも僕の手を強く握り、「一番になれ」と熱く語った。
Tさんは実力あるドラマ監督だったが、実力では劣るのにTさんよりも有名な監督が、業界にはたくさんいた。
そういう人たちに負けたことが、たぶんTさんは悔しかったのだ。
僕のテレビ業界での成功を、Tさんは本気で考えてくれているようだった。
その期待に応えるために、僕はますます努力した。
ドキュメンタリーディレクターに昇格
それからしばらくして、僕は派遣ディレクターとして、ある会社で働けることになった。
Tさんが、その会社に僕のことを紹介してくれたのだ。
20代のうちに助監督からディレクターに昇格できるとは思っていなかったので、僕は驚き、とても喜んだ。
新米ディレクターの僕に任された仕事は、深夜放送の音楽ドキュメンタリー番組を撮影・編集することだった。
僕の人生の中で、最も忙しい日々が始まった。
毎日重たいビデオカメラを携えて、都内のライブハウスや地方の音楽イベントを取材した。
取材相手は、売り出し中のアイドルや実力派ロックバンド、弾き語りのシンガーソングライター、ヘヴィメタ姉ちゃん、クラブDJ、レゲエのおっさん、色物お笑い企画ユニットなど多岐に渡った。
僕は自分で撮影した玉石混交の映像を会社に持ち帰り、パソコンですぐさま編集した。
低予算のためスタッフの人手が足りず、いつも締め切りギリギリで作業した。
徹夜の連続で、ほとんど家に帰れなかった。
仕事のきつさに耐えかねて、アルバイトのADはしょっちゅう辞めていった。
だが、僕はその状況をあまり辛いとは思わなかった。
むしろ、楽しんでいた。
千本ノックのように毎日撮影・編集しているうちに、僕はだんだんドキュメンタリー制作の虜になっていった。
とりとめのない現実を映像で切り取り、編集で一本筋が通ったストーリーを作り上げることに、僕は生きがいとやりがいを感じ始めていた。
私生活でも変化があった。
死ぬほど忙しい仕事の合間をぬって、僕は3歳年下の女性と結婚した。
あまりに僕が忙しすぎたので、結婚式の準備や段取りはほとんどすべて妻がやってくれた。
まったくいい人をお嫁にもらったものだ。
新郎側の挨拶はTさんが引き受けてくれた。
結婚式から1年後、我が家に待望の長男が生まれた。
僕の人生は、まさに順風満帆に見えた。
Tさんとのすれ違い
その一方で、うまくいかないと思うこともあった。
Tさんとの間に、だんだんすれ違いを感じるようになっていたのだ。
Tさんは時々、僕の派遣先に様子を見に来てくれた。
最初は僕もそれが嬉しかったのだが、ドキュメンタリーが面白くなるにつれて、不敬にも僕はTさんの存在をうざったく感じ始めていた。
Tさんの口癖に耳が痛かったからかもしれない。
Tさんは来るたびに「ドラマの企画書を出せ」と言ってきた。
企画書の重要性は、僕もよく理解していた。
だが、ドキュメンタリーに夢中な僕には、それを書く余裕なんて全くなかった。
だから、僕はいつも適当に生返事するしかなかった。
そんな僕の態度の変化を感じたのだろう。
Tさんが僕の会社を訪れる回数は、だんだん少なくなっていった。
僕は、ドラマの企画書を書けないことを申し訳ないと思いつつ、その代わりに派遣先で大量の短編ドキュメンタリーを作った。
その数は2年間で200本を超えた。
作品の出来栄えに感動したアーティストやそのファンたちから感謝されることも多かった。
それが快感で、僕はますますドキュメンタリー制作の魅力にはまっていった。
そんなある日のこと、僕は久しぶりにTさんから呼び出しを受けた。
呑気に待ち合わせ場所へ出かけた僕を待っていたのは、突然の解雇通告だった。
【第3回へと続く】





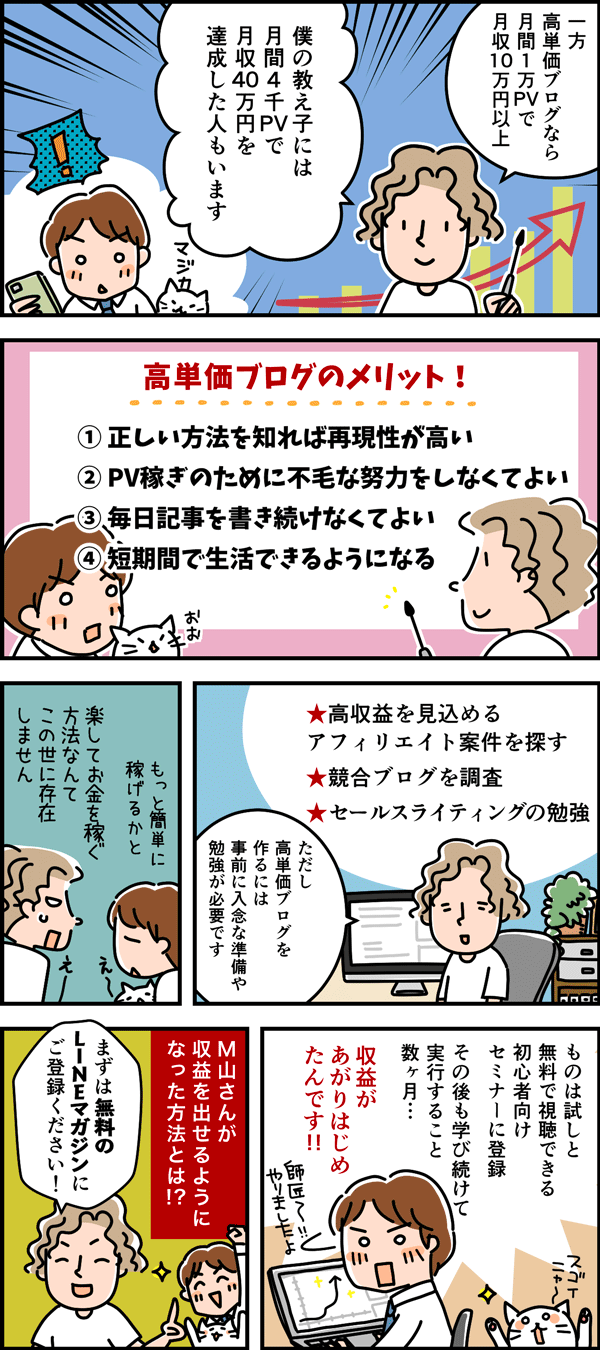





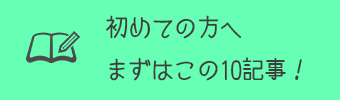
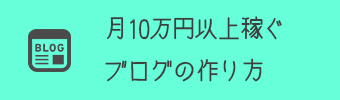
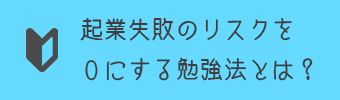
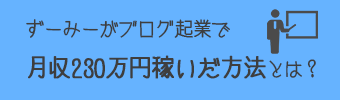
わ~、この記事を読んで良かった~!本当に「物語」っておもしろいですね。
ずーみーさんが何度も言っていた「突然クビ」の謎が解けます。
当時のずーみーさんには申し訳ないですが…ワクワクしながら次の記事へ進みます。