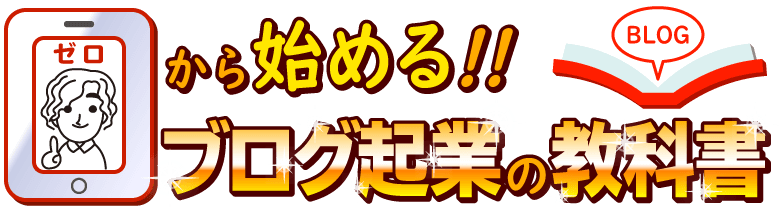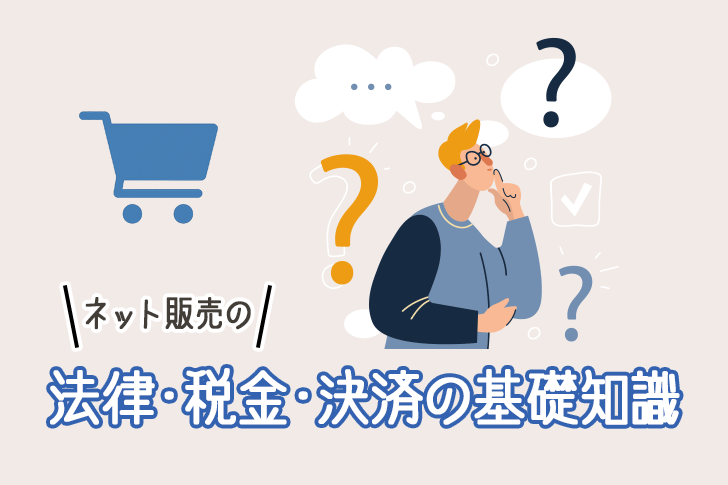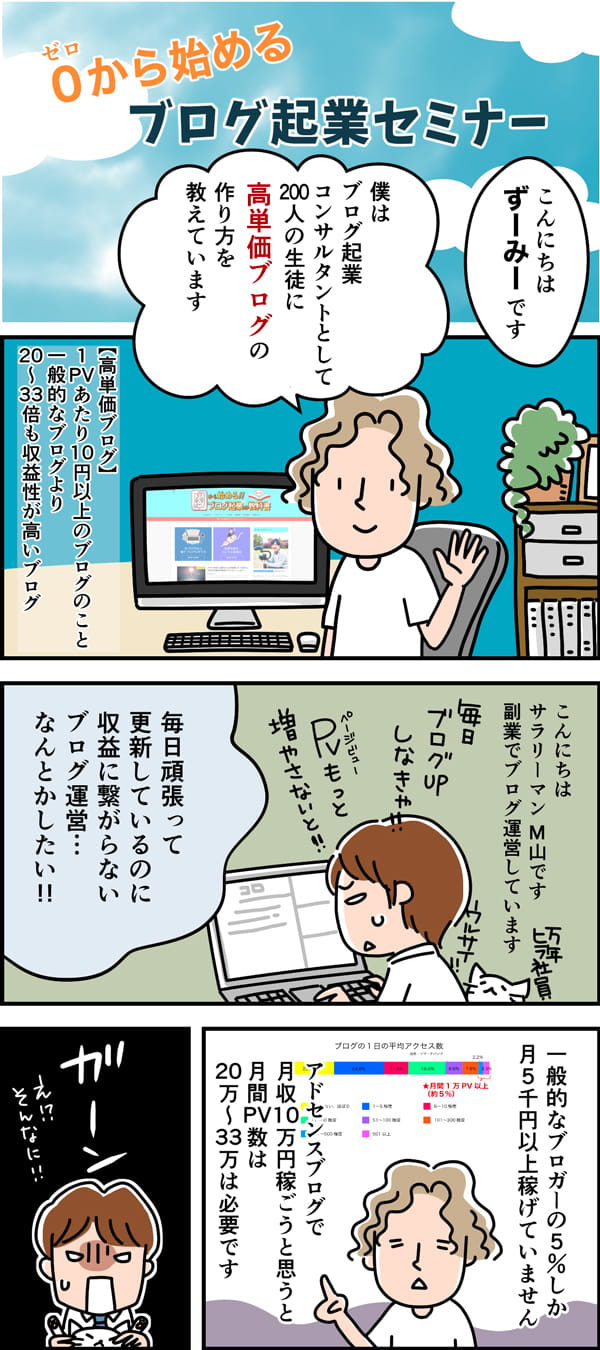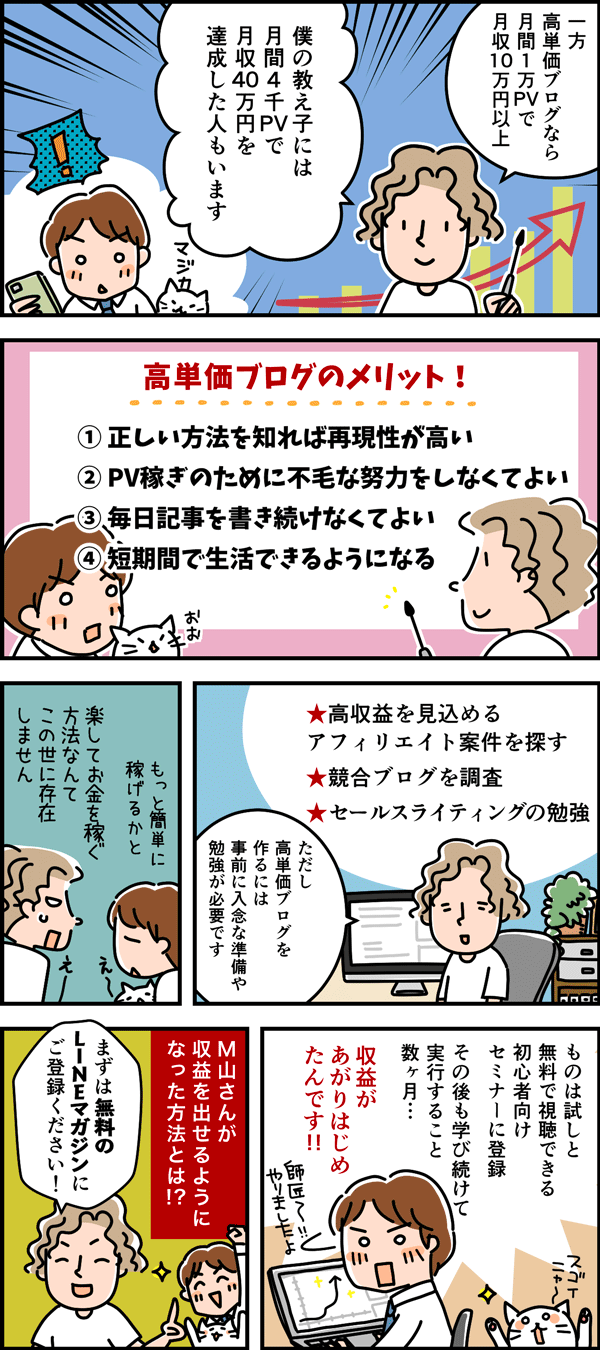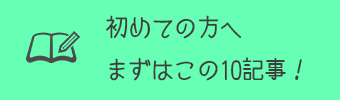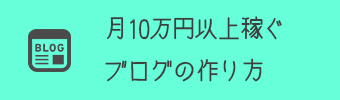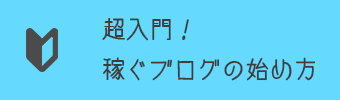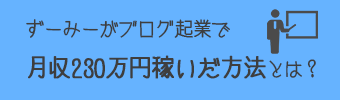自分の商品をネットで売り始めようとしたとき、こんな不安はありませんか?
「本名や住所をネットに公開しなきゃダメなの?」
「確定申告って必要? 副業がバレたらどうしよう…」
「PayPalがBANされるって本当?決済サービスはどれを使えば安心?」
ネット販売は手軽に見えて、いざ始めようとすると、法律・税金・決済などの“見えない不安”が次々に浮かんできて、なかなか一歩が踏み出せないものです。
とくに、オンライン講座やPDF教材などのデジタル商品を売りたい方や、副業としてブログやLINEを使って商品を販売したい方には、
- 個人情報を出すのが怖い
- 会社にバレずに続けたい
- 決済トラブルやアカウント停止は避けたい
そんな不安がつきものではないでしょうか?
この記事では、ネット販売を始める前に最低限知っておきたい「法律・税金・決済」の基礎知識を、初心者にもわかりやすくまとめました。
安心して一歩を踏み出すためのチェックリスト代わりに、ぜひ最後までお読みください!
詳しい目次
ネット販売に必須!特定商取引法のルールと対策まとめ

ネットで商品を売るのは手軽ですが、実は守らないといけない法律やルールがいくつかあります。
その中でも特に重要なのが、「特定商取引法(略して“特商法”)」。
この法律は、ネット通販はもちろん、LINE販売・ブログ・BASE・STORESなどを使って商品やサービスを販売するすべての人が対象になります。
特定商取引法(特商法)とは?
特定商取引法(特商法)は、たとえばネットショップやカタログ通販など、対面しない形で商品を販売する際に起こりやすいトラブルを防ぐための法律です。
販売者は、購入者が安心して取引できるように、以下の情報を表示する義務があります。
- 販売者の名前(本名、または屋号)
- 住所(所在地)
- 電話番号(問い合わせ先)
- メールアドレス
- 返品・キャンセルの条件
- 販売価格・送料・支払い方法 など
これらの情報は、「特定商取引法に基づく表示」として、販売ページやプロフィールからすぐ確認できる場所に記載しておく必要があります。
「面倒だな…」と思うかもしれませんが、これは法律上の義務。
違反すると行政指導や罰則のリスクもあるので、しっかり対応しておきましょう。

僕もネットで商品を売り始めた当初、「えっ、個人情報を開示しなきゃいけないの?」と焦った経験があります。
あとから慌てないよう、販売を始める前に準備しておくと安心ですよ!
本名や住所を載せたくない場合はどうする?
個人情報をネット上に載せるのが不安なのは、とても自然なことです。
特商法では「名前・住所・電話番号」の公開が原則ですが、実は「屋号(ビジネスネーム)」を使ったり、「バーチャルオフィス」を活用したりして、本名や自宅住所を隠す方法もあります。
- 屋号の取得(ビジネスネームを使う)
本名の代わりに「○○ショップ」などの屋号を表記できる。屋号自体は届出なしでも名乗れるが、銀行口座を作りたい場合は開業届が必要。 - バーチャルオフィスを契約する
月数千円程度でレンタルできる住所を使用することで、自宅の住所を公開せずに済む。

特に副業や女性の個人事業主さんで、本名や住所を公開したくない人には、バーチャルオフィスの利用が人気です。
僕のコンサル生でも実際に使っている人がいます。
特商法のルール違反で起こるトラブル例
もし特商法の表示義務を怠ると、法律上だけでなく、ビジネス面でも大きな不利益につながる可能性があります。
たとえば、以下のようなトラブルが起こることも…
- 行政からの指導や罰則(最悪の場合は業務停止命令も)
- 購入者との信頼関係を損ねて、クレームが大きくなりやすい
- 決済サービス(PayPalやStripe)でアカウント制限や凍結のリスクが高まる
特商法は、法律だから仕方なく守るというより、“信頼される販売者”になるための第一歩と考えれば、きっと気持ちもラクになりますよ。
デジタル商品を売るときの注意点(著作権・NGジャンル)

特商法で販売者情報のルールを押さえたら、次に気をつけたいのが「売る商品そのものに問題がないか?」という視点です。
とくにオンライン講座・PDF教材・テンプレート素材などのデジタル商品を扱う人は、著作権や販売ジャンルのルールを知らずに始めると、思わぬトラブルにつながることがあります。
この章では、初心者がつまずきやすい2つの落とし穴についてわかりやすく解説します。
他人の素材や文章を使っても大丈夫?著作権の基本
「全部自分で作ったつもり」でも、知らず知らずに他人の著作物を使ってしまっているケースは意外と多いです。
たとえば、こんな事例は要注意です。
- フリー画像サイトで見つけた素材を、PDF教材にそのまま使った
- 他人のブログや本の内容を参考に、そっくりな文章でまとめた
- ChatGPTなどのAIで生成した文章を「完全オリジナル」として販売した
こうした素材は、ライセンス条件や引用ルールを守らなければ“著作権侵害”と見なされることもあります。
著作権で気をつけたい3つの基本ルール
| ルール | 内容 |
|---|---|
| ① 引用は「条件付きで許される」 | 出典の明記・量のバランス・主従関係が必要 |
| ② フリー素材でも「商用利用OKか」を確認 | 「商用不可」「改変禁止」などの注意書きに要注意 |
| ③ AI生成物は“著作権のグレーゾーン” | 元データが著作物に類似しているとリスクになることも |
特に、販売目的で使う場合は「無料で使えます」と書かれていても“商用利用OKかどうか”は必ず確認しましょう。

フリー素材で有名な「いらすとや」は商用利用OKですが、「1つの制作物に20点まで」という上限ルールがあるのを知っていますか?
商品が売れてから気づくと、対応も大変なので、最初の段階で素材のルールを確認しておくのが安心ですよ!
医療・金融・R18など「規約で禁止されたジャンル」に注意
もうひとつ気をつけたいのが、「そもそも販売できない・審査に通らないジャンルを扱っていないか?」という点です。
これは法律違反というより、決済サービスや販売プラットフォーム側の「利用規約」や「ポリシー」に引っかかるケースが多いです。
特に注意すべきジャンル例
| ジャンル | 規制される理由/リスク |
|---|---|
| 医療・健康系(例:便秘解消・体質改善) | 薬機法違反のリスクあり。効果効能をうたう表現は特に注意 |
| 投資・お金系(例:FX・仮想通貨・副業) | 金融商品取引法や詐欺対策の観点から審査が厳しく、規約違反になることも |
| アダルト・性的コンテンツ | 多くの決済サービス(PayPal・Stripeなど)で明確に禁止。審査落ちやアカウント凍結の可能性あり |
これらのジャンルは、「売ってはいけない」わけではありませんが、言葉の選び方ひとつで、決済サービスのアカウント凍結や、販売停止になる可能性があるので慎重に対応する必要があります。
また、販売ページでの以下のような表現も、規約違反や法令違反としてアカウント凍結につながる恐れがあります。
「これぐらいなら大丈夫でしょ…」と思って使った表現が、アカウント凍結や返金トラブルの原因になることも。
少しでも不安な表現があれば、事前に規約やルールを確認しておきましょう。
副業と税金:確定申告とバレないための対策

法律や商品内容のチェックが終わったら、次に気になるのが「税金」や「副業バレ」の問題ではないでしょうか?
- 売上が出たら確定申告って必要?
- 会社にバレずに副業を続けるにはどうしたらいい?
この章では、ネット販売に関係する税金の基礎知識と、副業バレを防ぐ仕組みについて、初心者にもわかりやすく解説します。
副業でも確定申告は必要?目安は「年間20万円の利益」
会社員が副業としてネット販売を行う場合でも、年間の「所得(利益)」が20万円を超えると、確定申告が必要になります。
よくある誤解に、「売上が20万円を超えたら申告が必要」というものがありますが、正しくは、
売上 − 経費 = 利益(所得)
この利益が20万円を超えるかどうかで判断されます。たとえば、
- 売上30万円 − 経費15万円 → 利益15万円 → 申告不要
- 売上50万円 − 経費25万円 → 利益25万円 → 確定申告が必要
アフィリエイト報酬やnoteでの販売収入なども、もちろん対象です。

ネット収入って、実は税務署からけっこう“見えやすい”んですよね。
「副業だし、ちょっとしか稼いでないから…」と油断せずに、ルールは最初に押さえておきましょう!
副業が会社にバレる最大の原因は「住民税」
「確定申告したら、会社に副業がバレるんじゃ…?」
こんな不安を抱える人は多いと思いますが、実は“確定申告したこと自体”でバレるわけではありません。
バレる最大の原因は、“住民税の通知が会社に届く仕組み”にあります。
バレる仕組みを簡単にいうと…
会社員の住民税は、翌年6月ごろから給料から自動的に引かれます(=特別徴収)。
ここに副業の確定申告分が加算されると、自治体が“会社あてに”その総額を通知してしまうんです。
- あなたが確定申告する
- 税務署→自治体へデータが送られる
- 自治体が「本業+副業ぶんの住民税額」を会社に通知
- 経理担当「えっ、この人住民税多くない?」→ バレる
バレないようにするには?普通徴収でOK!
安心してください。対策はとてもシンプルです。
確定申告書の中で【住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」にチェック】するだけ。
- 国税庁の確定申告書作成コーナー or e-Taxで申告書を作成
- 「住民税に関する事項」で【自分で納付(普通徴収)】にチェックを入れる
→ これで副業分の住民税は会社を通さず、あなたの自宅に直接届くようになります。
重要:会社の経理に「普通徴収にしたいんです」と言う必要はありません。
それを言ってしまうと「副業してます」と自ら伝えることになるので逆効果です。
また、住民税以外にも、ブログやSNSのアイコンが本人に似すぎていたり、発信内容が原因で副業バレするケースもあります。
会社にバレたくない方は、くれぐれも気をつけてくださいね。
開業届は出すべき?節税面でのメリットが大きい!
「開業届って出したほうがいいの?出したら会社にバレない?」という疑問もよく聞きます。
結論から言うと、開業届を出しただけでは会社に通知が行くことは基本的にありません。
また、出さないと違法というわけでもありません。
開業届を出す主なメリットは以下の通りです。
- 青色申告(最大65万円の控除)で節税効果が大きい
- 屋号で銀行口座を開設できるようになる
- 「ちゃんと事業してます」と見なされ、経費の説明が通りやすくなる
とくに、今後ネット販売を本業に近づけたい方や、節税もしっかりやりたい方にはおすすめです。
決済サービスの選び方と“BAN対策”の基本

法律や税金の不安を乗り越えて、「さあ、販売を始めよう!」となったときに次にぶつかるのが、決済サービスの選び方ではないでしょうか?
特にデジタル商品を売るなら、クレジットカード決済は必須レベル。
「PayPalってBANされるって本当?」
「Stripeとどっちが安全?」
「銀行振込だけじゃダメなの?」
そんな不安や疑問に答えるべく、ここでは初心者におすすめの決済方法と注意点、凍結を避けるための対策をまとめました。
決済サービスを導入する理由と選び方の基本
ネット販売を成功させるには、お客様がストレスなく支払える仕組みを整えることが重要です。
とくにクレジットカードやスマホ決済に対応しているかどうかで、購入率に大きな差が出ることも。
- クレジットカード決済(Stripe/PayPal/Squareなど)
- 銀行振込(個人間で可能だが手動確認が必要)
- コンビニ払いやキャリア決済(BASEやSTORESなどを利用する場合に対応)
- 分割決済(Stripe・PayPalは「定期支払い機能」で擬似的な分割にも対応可)

高額商品の成約率を上げるなら「分割決済対応」のサービスを選ぶのがコツです!
初心者が使いやすい主要決済サービス3つ
初心者が使いやすい決済サービスとしては、Stripe・PayPal・Squareが有名です。
手数料はどれも約3.6%前後と大きな差はありません。
選ぶときのポイントは「審査の厳しさ」や「販売ジャンルとの相性」です。
- Stripe(ストライプ)
・クレジットカード決済に強く、サブスクやLINE連携もOK
・デジタル商材との相性が良く、審査も通りやすい印象 - PayPal(ペイパル)
・世界的に信頼されていて導入も簡単
・ただし、副業系・情報商材・R18系には厳しめ。BAN報告もあり - Square(スクエア)
・小規模のオンライン販売や対面販売向き
・機能はシンプルで、審査は比較的やさしい

どれにするか迷ったら、初心者は「Stripe」を選ぶのがおすすめです!
StripeはBANリスクが低く、個人事業者にも向いています。
PayPalでアカウントが凍結される理由と対策
「PayPalでアカウントが凍結された(=BANされた)」という話、聞いたことありませんか?
実際、PayPalでは「ある日突然アカウントが使えなくなる」といった事例が報告されており、引き出し停止や最悪資金没収のリスクもあります。
とはいえ、正しく使えば問題なく利用できている人も多いのも事実。
大切なのは、凍結の原因を理解し、安全な運用を心がけることです。
よくあるBANの原因
以下のような状況は、凍結リスクを高めるとされています。
- 副業系・投資系・R18など、規約で禁止されているジャンルでの販売
- 「絶対に稼げる!」「100%保証!」といった誇大広告や曖昧な表現
- 特商法の表示やキャンセルポリシーが不十分な販売ページ
- 本人確認や銀行口座登録を後回しにしている
- 購入者とのトラブルや返金申請が多い(=顧客満足度が低い)
アカウント凍結を防ぐ5つのポイント
- 販売ジャンルが規約に違反していないかを事前に確認
- セールスコピーは誇張せず、誠実な表現で
- 特商法のページ、返金・返品ルールをしっかり明記する
- 顧客対応を丁寧に行い、トラブルやクレームを最小限に
- 本人確認・銀行口座の登録は早めに済ませておく
これらの点に注意し、きちんと準備して販売を始めれば、アカウント凍結を心配しすぎる必要はありません。
よくある質問(Q&A)

ネット販売を始めるときに多くの方が感じる「これってどうすればいいの?」にお答えします。
詳細を知りたい方は、回答をクリックしてご覧ください。
詳細を知りたい方は、回答をタップしてご覧ください。
まとめ:安心してネット販売を始めよう!
今回は、ネット販売を始めるにあたって押さえておきたい「法律・税金・決済」の基礎知識を解説しました。
- 特商法で必要な表示ルール
- デジタル商品に関わる著作権とNGジャンル
- 副業バレを防ぐための税務対策
- PayPalやStripeなど決済サービスの選び方と注意点
どれも一見むずかしそうに思えるかもしれませんが、事前に正しい知識を持っていれば、トラブルや不安を減らすことができます。
ネット販売は、自分の知識やスキルを活かして自由に働ける、とても魅力的な手段です。
この記事を読んだあなたが、自信を持って一歩を踏み出せることを願っています!